マンネリスナップ脱却のヒント:「観察の練習」で鍛える見る力
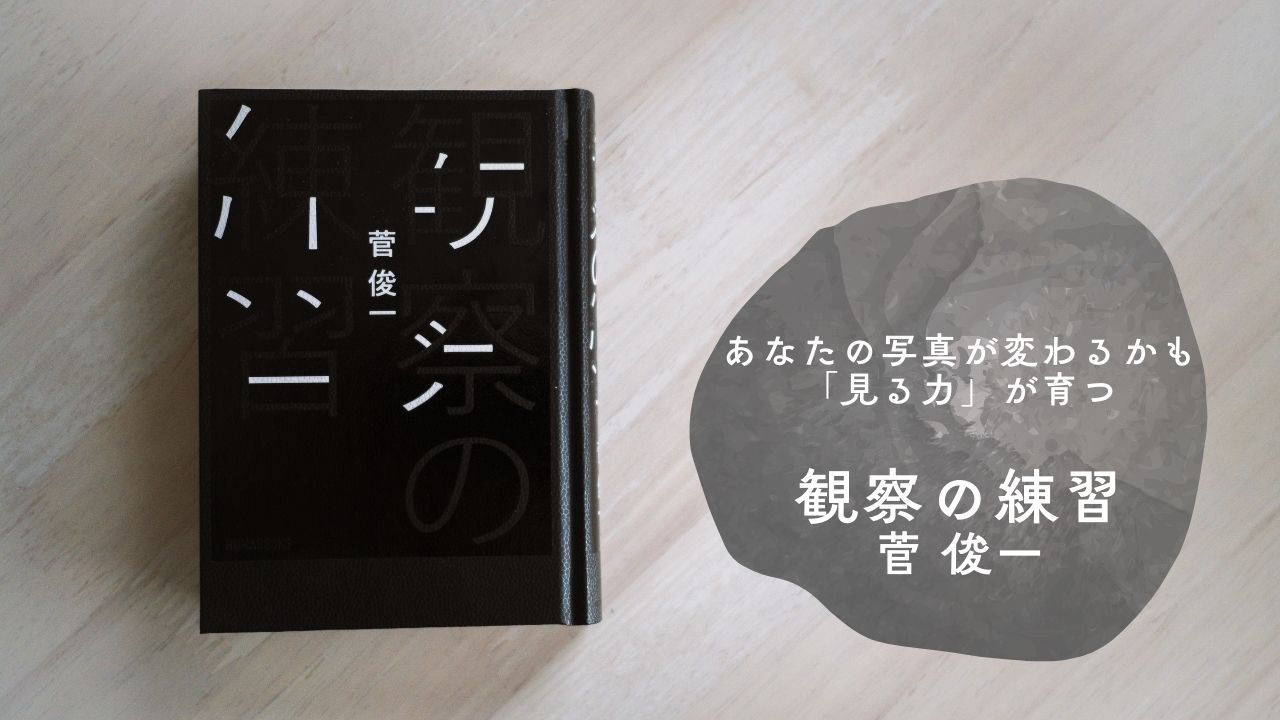
私は普段、景色やスナップ写真を撮ることが多いです。
ポートレートでは被写体となるモデルがはっきりとしていますが、景色やスナップ写真は何を被写体にしてもいい。
※もちろんマナーは守った上での話ですが。
では何を被写体にするか。それを考える上で大事なことの一つは「観察」であると私は考えています。
今回はそんな「観察」についての書籍、菅 俊一さんの「観察の練習」を紹介します。
この本は「観察」という行為を「練習」する目的で書かれています。
- いつも同じような写真を撮ってしまう
- 撮りたいものが見つからない
- 自分の写真に新鮮味がない
このように感じている方は、この本を読んでみると今までとは違った視点で写真を撮れるかもしれません。
観察とは、日常にある違和感に、気づくこと
この本の冒頭の言葉です。
日々繰り返される行動、いつも目にする風景、そんな何気ない日常に隠れている「違和感」
この本は、著者がそんな日常の中で感じた小さな「違和感」を集めたものです。その数56個。
本書の構成は、まず著者が実際に違和感を覚えた写真が提示され、次のページでどこに違和感を抱いたのか、その理由が説明されているという形式。
つまり、読者もその写真を見て、著者が何に違和感を感じたのか一緒に考えることで、観察する練習ができる構成になっています。
解釈の正解はなく、著者との着眼点や考え方の違いも含めて、なるほど!と思わせてくれる本であり、
・忙しい日々の中で注意力が散漫になっている
・先入観や固定概念により、考えが凝り固まっている
そんな「違和感」以外の気づきも与えてくれる本です。
実際に観察して見えてきたもの
この本を読んだ後に、カメラを持って出かけてみました。
その際にふと目に止まった「違和感」を撮ってみました。
コンクリートの支柱


ただのコンクリートの支柱。ひび割れもあり、随分昔に作られたものだと思います。
ただ、よく見ると表面に滑らかな凹凸やところどころに木の節があったり、僅かに残った塗装のあとが。作られた当初は木を模した見た目をしていたのかなと想像でき、ひび割れも相まって時の流れが垣間見える一本。
歩道脇の木々


歩道のそばに植えられている木々。その中で異なる種類の木が超至近距離で生えていました。
一度素通りしたあとに、「え、近くない?」と思い写真を撮りました。
歩道に並ぶのは太い方の木であり、太い方は人工的に植えられたんだろうなと。
では細い方は?そもそもこんな至近距離で木は育つのか?土の中の根はどうなってるの?
いろいろ疑問が出てくる不思議な木々。
サイクルロードに掲げられた看板

ぱっと見たときは何も違和感を感じない。
ただよく見ると、自転車も車輌だろ!そんな屁理屈を言われそうな看板。
そんな野暮なことは言わないけど、無意識に車輌=自動車に変換しているんだと気づいて撮った一枚。
こういった、「無意識」に「意識」できるようになると、面白い写真が撮れるかもしれない。そんな気づきも与えてくれた看板。
写真を撮る前に周囲をよく観察してみよう
今回は「観察の練習」という本を実際に読んで、私が何に気づいたかを紹介しました。
いい写真が撮りたいと思うと、いい被写体はないか、いい景色はないかとついつい探してしまいます。
ただ、写真を撮る撮らない関係なく、まずは周囲をよく観察してみると、意外な気づきがあり、思ってもないような意外な写真が撮れるかもしれません。
・この世界には、わたしたちが気づかず、見過ごしているものがたくさんある
・いつも見ている景色や日常の中にも面白いものはたくさんある
「観察の練習」は、そんな気づきを与えてくれます。
撮影技術や知識についての本ではありませんが、この気づきが写真に変化を与えてくれるかもしれません。
写真を撮らずとも面白い本ですので、気になった方はぜひ手にとって読んでみてください!



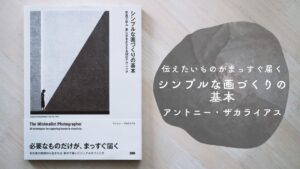
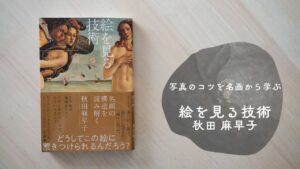
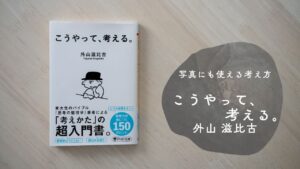
コメント